正門をくぐると通りの左右に軒を並べる商店街が目に入る。まだ午前も早いので足の踏み場もない、というわけでもないが、道具屋の前には人だかりが出来つつある。店先に並べた台の上にある布地を両手で広げている者や、籠細工を手に取って丹念に眺めている者がいる。鍛冶屋の前には布で包んだ武器を抱えた冒険者たちが数人、早くも列を作っている。薬草を商う店の前には一山幾らで売られる香草の束が置かれていて、これを吟味する者が匂いを嗅いでいる。その奥には分銅を乗せた秤が日光を反射して光っている。 街のほぼ中央に噴水広場がある。 砂岩煉瓦の支柱が白い水盤を手の届かない高さに固定していて、その縁から水が滴り落ちている。落ちた水は水溜りで飛沫をあげている。この水溜りも色目の白い砂岩煉瓦でぐるりを囲まれていて、澄んだ水が支柱の排水口に落ちて小気味良い音をさせている。水は街の高台にある泉から建物の壁に沿った樋で延々と引き込まれていて、噴水広場の一番近くに建つ道具屋の建物から中空を渡って水盤の上まで差し渡してある。 噴水周囲の広場では露店を出す者が場所取りを始めていて賑やかである。小さな屋根のついた屋台では燻製肉を釣り下げて下から炙る炉に火を入れている。肉を削り取る細長い包丁と長い木串がすでに台の上に乗せてあり、通りすがりの人が匂いにつられて思わず足を止めている。その隣に段違いの縁台を広げている者は、そばに大きな麻袋を幾つも並べていて、袋の口から真っ赤な林檎や黄色い柑橘の実がこぼれ落ちている。 イルファーロの街に来ると、子供のように心が浮き立つ。 町人も旅人も冒険者も、決め事さえ守るなら等しく自由に振る舞うことが出来る快適な場所だ。いきなり刃物を突きつけられることもないし、まとわりついて金品をねだってくる奴もいない。もちろんイルファーロに犯罪がないわけではない。しかし武装した衛兵が要所に立ち、決まった時間に巡回をしているということは、市井の人々にとっては頼もしいことだ。 正門から真ん中の通りを歩いて噴水広場まで来ると、道が分かれて商店の数と売物の種類がぐんと増える。そのうち右手、東へ向かう道の角には革物屋があり、店先に陳列台を出して鞄や靴、帯といった品を並べている。その辺りに人垣が出来ていて、姿は見えないが大声で瓦版を売っている者がいる。何か事件があったのだろう。人混みは避けたいところだが、どのみちその先にある酒場に用事があるので仕方ない。ルメイがついてくるのを振り返って確かめてから、そちらに向かって歩いた。 人の波にもまれてゆるい坂を上がるうちに、瓦版売りの大声が否応なく耳に入ってくる。男は壁際の台の上に乗り、手にした瓦版の束を叩いて調子を取りながら朗々と口上を垂れている。 「さあさあ買った買った号外だ、ネバがやったよまたやった、徴税官の金の延べ棒三十本、今度は女剣士イレーネも一緒だよ。ネバの懸賞金はなんと金貨千八百枚、イレーネの懸賞は千二百、二人合わせて三千枚だ。詳しくはこちらの瓦版、これがたったの銅一枚」 瓦版は読まずともほぼ判る。山賊一味が護衛付の輸送馬車を襲撃して金を奪ったのだろう。ゴシップが嫌いな訳ではないが、今は瓦版に銅貨一枚は出せない。 人だかりをかき分けて坂道を登りきると、大きな酒場の前に出た。一階部分は砂岩煉瓦を積み上げてあり、軒先にはブリキの大ジョッキが釣り下げてある。二階は荒削りの木材で増築してあり、大きな入口から覗き込めば壁際に付けられた階段が見える。酒場は朝から開いており、午前と午後でメニューを変えながら夜遅くまで店を開けている。中に入ると看板娘のマリーがいらっしゃいませと声をかけてきた。襞のついた薄桃色のスカートに青いチョッキを羽織っていて、白いカチューシャで栗色の髪をまとめている。すでにいくらか客が入っており、マリーは手にした盆を持って二階に上がって行った。 酒場の一階にはテーブル席がない。左手に階段、その奥に厨房が見え、右手奥には金を払うカウンターがある。カウンターはそのまま部屋の右側を回り込んで入口まで続いている。取り急ぎ食事だけしたい客はこのカウンターで食事をすることが出来る。ゆっくり食事をしたい客は二階のテーブル席に行く。部屋の中央がどうなっているかと言えば、床を張ってない土間に、背もたれのない小さな椅子が幾つも並んでいる。早立ちをするには遅い時刻なので今は四人の男が座っているだけだが、早朝などはここに大勢の冒険者が詰めかける。一緒にパーティーを組む相手を探しに来るのだ。めいめいが声をかけあうと怒鳴りあいになってしまうので、それぞれカウンターでメモを書いて酒場の読上げ係に渡す仕組みになっている。読上げ係は誰かが来るたびに、手元のメモを大声で読み上げる。俺とルメイが椅子に座ると、カウンターの奥にいた男がメモを片手に出てきた。ひとつ咳払いをしてからその場にいる男たちに募集の内容を読み上げる。 「今かかってる募集は三件。 一つ、剣士を募集、協会依頼をこなす長期パーティー、報酬差額有り。 二つ、当方杖使い、協会依頼をこなす長期パーティーを募集。 三つ、雑用と荷役募集、住み込み可、黒鹿亭」 とりあえず、黒鹿亭の仕事はごめんだ。黒頭巾の連中と一緒に働くなど考えられない。剣士の募集があるが、報酬差額有りというのが気に入らない。元々のメンバーが割り良く取って、新入りはほとんど貰えないのが常だ。おそらくルメイなどはすぐに締め出されてしまうだろう。杖使いをパーティーに入れるのはどうだろうか。俺は冒険者協会に登録していないので協会依頼はやらないが、コボルトを楽々狩れるパーティなら文句はなかろう。俺は立ち上がって読上げ係に声をかけた。 「杖使いのを見せてくれ」 男が手渡してきたメモを指でひろげて募集の詳細に目を通す。 ① 募集人 S・アルゴン(杖使い) 協会登録済 ② 得手 火炎を二十歩先まで、簡単な罠の設置 ③ 報酬分配 半分 ④ 連絡先 黒鹿亭に逗留中、いつでも声をかけてくれ! メモを記録係に突き返す。この男は知っている。いけすかない杖使い野郎だ。以前、剣士三人で力押しの狩りをやっていた時、四人目のメンバーとして加入してきた。当時のパーティーのリーダーは剣の腕はそこそこだったが、金属性の鎧の上下一揃いを所有していて、乱戦に強い奴だった。威勢が良くて狩場ではいつも先頭に立ち、危なくても実入りの良い狩場を好んだ。防御の堅いリーダーの左右に俺とロニーが回り込んでモンスターを殲滅した。そういえばロニーはいい奴だったな。今頃どこにいるのか。 新入りのアルゴンは後ろから杖を使って攻撃した。杖を振ると火の玉が出てよい牽制になった。致命傷を与えるような威力はないのだが、魔法で攻撃されるとモンスターはそちらばかり気にするので隙が出来る。それは良いのだが、アルゴンは自分が攻撃にさらされないように俺とロジャーの立ち位置に細かい指示を出す面倒な奴だった。そのうえ、いつも山分け以上の報酬を要求して不満を鳴らした。今ではそれを堂々と主張しているらしく、メモにあった報酬分配の半分とは、実入りの半分は俺が頂くから残りをお前らで山分けしろ、という意味だ。 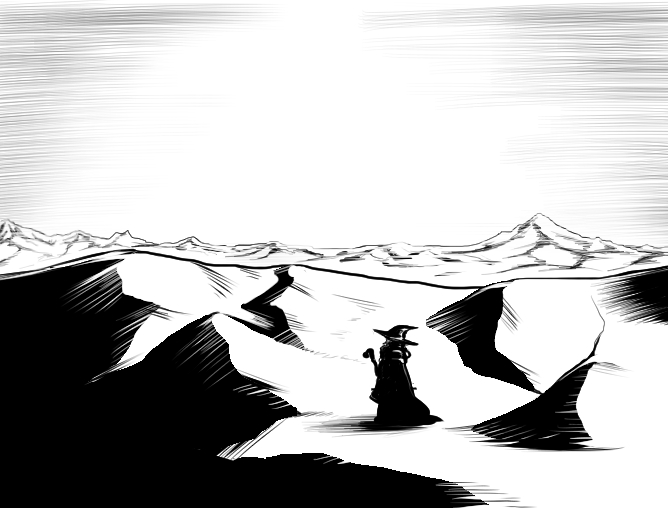 今の時代に、本物の魔法使いはいるのだろうか。 王直属の機関である魔法局あたりにはいるのかもしれない。しかし冒険者たちの中で魔法を使って攻撃する者のほぼ全ては、杖使いと呼ばれる。かつて魔法の体系を解明したドラグーン人が大陸を支配していた時代、世の中には多くの魔法使いがいたという。彼らは火の玉を飛ばし、遠くの敵を氷結させ、自由に霧を生じせしめたという。さらには魔法を使うのに都合の良く加工した杖を作った。その杖を振れば初心者でも魔法使いの真似事が出来る。 その魔法の杖が古代の遺跡から掘り出されている。魔法の杖の所有者は呪文を唱え、杖を振って魔法攻撃が出来るようになる。向き不向きがあって杖を使いこなせない者もいるので、本人の力が全く関係ないというわけではないが、その威力は杖の性能によると言われている。魔法の杖は恐ろしく高価だ。それを手に入れる財力のある者か、幸運に恵まれて遺跡の宝箱などから杖を手にいれた者が杖使いになることが出来る。たいていひと癖ある連中ではある。 再び椅子に座りこんでちらりと周囲を見る。ここに残っている俺たち以外の連中も、今かかっている募集に飽き足らず次の募集を探しているはずだ。 「カリグラーゼ辺りの林でコボルトを狩ろうと思うんだが、剣士二人に合流してくれる方はおらんかな」 隣の男はすまなそうに手を振ってみせた。その隣の男も首を横に振っている。奥にいた男は潮時とみて立ち去ってしまった。もう少し待ってみるかなと思っていると、ルメイの腹がぐうと鳴った。ルメイは他人の体を見るように自分の腹を見ている。そういえば俺たちは朝から井戸の水を飲んだきりだ。途中で岩場に寄り道をして、ここまで歩き通してきた。酒場の厨房からは肉の焼ける音と匂いが届いていて、胃が熱くなるような感覚に身をゆだねている。何かを腹いっぱい食べたいという気持ちでいるうちは、落ち着いて何もすることが出来ない。手持ちの金を考えるとのんびり飯を食っている場合ではないという気もするが、よしと膝を叩いて気持ちを切り替えることにする。 (→つづき) |
| 戻る |